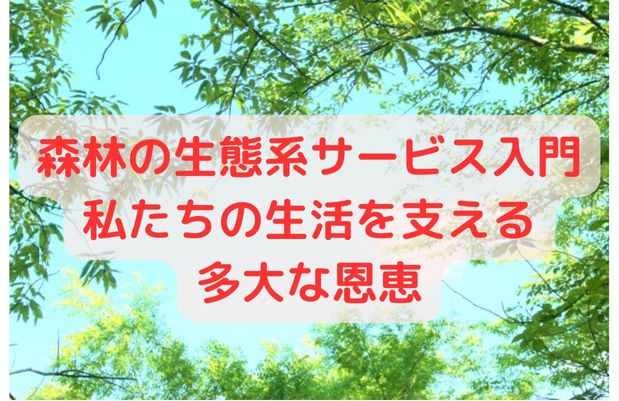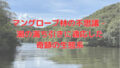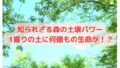私たちの日常生活は、木材や医薬品の原料から、きれいな飲み水、穏やかな川の流れ、爽やかな空気、そして植物を元気に育てる土壌まで、様々な形で森林の恵みに支えられています。これらの恵みの多くは普段意識されることはありませんが、その価値は計り知れないものです。
森林から得られるこれらの恵みは「生態系サービス」と呼ばれており、私たち人間の生活や経済活動に不可欠な役割を果たしています。日本学術会議による試算では、森林の持つ様々な機能の合計が年間約70兆円になると評価されています。しかも、生物多様性保全機能などはこの試算に含まれておらず、実際の環境価値はこの額をはるかに上回ると考えられています。
かつて自然の恵みは、私たちが利用する量よりも生態系が再生産する量の方が多く、無尽蔵に手に入るように思われていました。しかし現在では、人口増加や人類活動の拡大により、生態系の再生産力だけでは必要量や機能を賄えなくなってきています。「私たちが頼りにしてきた生態系サービスは、無限でもなければ、無料でもない」ということを人類はようやく認識し始めたのです。
本記事では、森林がもたらす多様な生態系サービスの種類、その重要性、そして私たちが森林の恵みを持続的に享受していくために何ができるのかについて解説します。
森林の生態系サービスとは何か

生態系サービスとは、生態系が人間にもたらす様々な恵みのことです。国連主導で行われた「ミレニアム生態系評価(MA)」では、生態系サービスを「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」、「基盤サービス」の4つに分類しています。また、「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」では、MAの分類を基本としながら、基盤サービスの代わりに「生息・生育地サービス」を追加しています。
森林の生態系サービスは、これらのカテゴリーに沿って以下のように整理することができます。それぞれのサービスについて詳しく見ていきましょう。
供給サービス – 森林から得られる物質的恵み
供給サービスとは、森林から直接得られる物質的な恵みで、人間の基本的な生存と経済活動に欠かせないものです。具体的には食品の提供(食用植物、きのこ、狩猟による獲物など)、建築材や家具などの原材料、繊維、染料、医薬原料、バイオマスエネルギーなどが含まれます。
木材・バイオマス資源
森林は私たちの生活に不可欠な木材や植物繊維、燃料などを供給しています。これらは建築資材や家具、紙製品、バイオマスエネルギーなど多くの用途に活用されており、森林面積の減少は直接的にこれらの供給低下につながります。
日本の木造住宅や伝統的な建築物、和紙や箸などの日用品から、最近注目されている木質バイオマス発電まで、森林資源は私たちの暮らしのあらゆる場面で活用されています。
食料・薬用資源
森林は食用となる植物や動物、きのこ類など様々な食料資源を提供するほか、医薬品の原料となる植物も多く生育しています。生物多様性が豊かな森林ほど、これらの資源も豊富に存在します。
山菜やきのこ狩り、ジビエ料理の材料となる野生動物など、森林は私たちの食文化にも大きく貢献しています。また、民間薬や漢方薬の原料となる植物の多くも森林に自生しています。
遺伝資源
森林に生息する多様な生物種は、農業や畜産業における品種改良のための遺伝資源としても重要です。生産量増加、病害抵抗性、栄養価の最大化、そして気候変動への適応など、これらの遺伝資源は将来的にますます重要性を増すと考えられています。
調整サービス – 環境を制御する森林の力

調整サービスとは、森林があることによって気候が緩和されたり、洪水が起こりにくくなったり、水が浄化されたりといった、環境を制御するサービスのことです。これらを人工的に実施しようとすると、膨大なコストがかかります。
気候調節機能
森林は光合成によって二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することで大気中の炭素バランスを調整しています。この働きは地球温暖化の緩和に大きく貢献しており、世界的な気候変動対策の重要な要素となっています。
また、森林は周辺地域の気温や湿度を調節する「緑のエアコン」としての役割も果たしています。都市部の緑地が「ヒートアイランド現象」を緩和する効果もこれに含まれます。
水源涵養・水質浄化機能
森林の土壌は、雨水を貯え、ゆっくりと河川に流す「緑のダム」としての役割を果たしています。また、森林の植生や土壌微生物によって水が濾過され、水質が改善されます。私たちの生活に不可欠な淡水を作り出し提供する生態系の能力は、樹木伐採や水質の富栄養化など人間活動から大きな影響を受けています。
災害防止機能
森林は根系や地表の植生によって土壌を固定し、土砂災害や洪水の防止に貢献しています。また、沿岸部の森林は津波や高潮の威力を弱める防波堤の役割も果たします。
研究によると、急傾斜地での伐採を避けることで土砂崩壊抑制機能の低下が軽減できることが示されています。このように、適切な森林管理は災害リスクの軽減に直結するのです。
文化的サービス – 心を豊かにする森林の価値

文化的サービスは、生態系が提供する精神的な豊かさや文化的な価値に焦点を当てています。これらのサービスは、人間の精神的な健康や文化的なアイデンティティの形成に寄与します。
レクリエーション・観光
森林は登山、ハイキング、バードウォッチング、キャンプなど様々なレクリエーション活動の場を提供しています。これを利用した旅行・観光ビジネスは経済的にも重要ですが、文化的サービスから得られる価値は目に見えにくい部分も多くあります。
日本では「森林浴」が心身の健康に良い影響を与えるとして広く実践されており、森林セラピー基地なども各地に整備されています。
教育・研究の場
森林は環境教育や生態学研究の重要なフィールドであり、次世代の環境意識を育む場所としても大切です。森の中での体験学習は、子どもたちの自然に対する感性や理解を深めるのに役立ちます。
文化的・精神的価値
森林は多くの地域で文化的・精神的な意味を持っています。日本においても、古くから森は神聖な場所として崇められ、鎮守の森や御神木などの形で保全されてきました。
また、森林は芸術や文学の創作意欲を刺激する源泉となり、多くの芸術作品や文学作品に描かれてきました。
基盤サービス(生息・生育地サービス) – 生命を支える森林の基本機能
前述のような生態系サービスを生物種がもたらしているため、それらのサービスの基盤となっている種の存続を助ける自然のはたらきそれ自体も、生態系サービスとみなすことができます。これを「生息・生育地サービス」と呼んでいます。
森林は多様な生物の生息・生育地となり、栄養循環や土壌形成、生物の送粉と種子の拡散など、他の生態系サービスを支える基盤的な役割を果たしています。自然は、生息環境を提供することで、生物が生存・繁殖できるようにしています。多様で広い生息環境があれば、多様な種や、種の中での遺伝的な多様性が存続できます。
環境の変化があった際に、似た生態系サービスを提供する種群のうちの一部が生き残る、あるいは種の適応進化が起こりやすく絶滅しにくくなります。結果、豊かな生態系を守ることが、生態系サービスを安定させることにつながるのです。
森林の生態系サービスの経済価値
生態系サービスの価値は簡単にお金に換算することはできませんが、日本学術会議による試算では、森林の持つ様々な機能の合計を年間約70兆円と評価しています。しかし、この試算には生物多様性保全機能などは含まれておらず、実際の環境価値はこれをはるかに超えるものと考えられます。
生物多様性や生態系サービスなどの「自然」の恵みのほとんどは市場で取引される価格が存在しないため、経済的価値を評価することは簡単ではありません。しかし、市場価値の存在する別のものに置き換えたり、人々に支払い意思額を尋ねたりと様々な評価手法が開発されています。
代替法による評価
代替法とは、生態系サービスなど自然環境が持つ機能を別の商品や施設等に置き換えるときの費用で環境の価値を評価する手法です。例えば、森林の水質浄化機能を評価する場合、同じ浄化機能を有する水質浄化施設を新たに建設した場合の費用(建設費やその後の維持管理費を含む)を求め、それを森林の水質浄化機能の価値とみなします。
支払意思額による評価(CVM)
環境改善に対する支払意思額や、環境悪化に対する受入補償額を尋ねることで環境の価値を評価する手法です。人々に環境の価値を直接尋ねるため、評価範囲が広く、景観、騒音防止、森林レクリエーション、水資源保全などの利用価値だけではなく、野生動物保護や生態系保全などの非利用価値も評価できます。
森林の生態系サービスが直面する課題

人口増加に伴い環境への負荷(エコロジカル・フットプリント)も増加しており、生態系サービスへの圧力が高まっています。多くの人々は、これらの生態系サービスが無償で、壊れることが無く、無限に利用できるという誤解に汚染されていましたが、人類による酷使の影響は絶えず明らかになってきています。
森林減少・劣化
世界的な森林減少は依然として深刻な問題であり、特に熱帯林では農地開発や木材伐採などにより多くの森林が失われています。日本においても、適切な管理が行われない人工林の増加や、過疎化による里山の荒廃が問題となっています。
生物多様性の喪失
平均すれば、1日あたり約100種の生きものが絶滅していると言われています。その大きな原因は人間による影響です。人間が森林を切り開くこと、里山に人が住まなくなったこと、外来種を自然の中へ持ち込むこと、そして地球温暖化の進行は、あらゆる生きものに大きな影響を与えています。生きものがいなくなれば、生態系サービスを受け取ることができず、私たちの暮らしを続けていくことはできません。
気候変動の影響
気候変動は森林生態系にも大きな影響を与えており、樹木の成長や分布範囲の変化、病害虫の増加、森林火災リスクの増大などの問題が発生しています。これらは森林の生態系サービス提供能力を低下させる恐れがあります。
森林の生態系サービスを持続的に享受するために
生物多様性や生態系サービスの価値を認識し、実際の保全につなげるためには、TEEBが提案する3段階のアプローチが参考になります。これは「価値の認識」「価値の可視化」「価値の捕捉」という段階を踏むものです。
持続可能な森林管理
日本国内では戦後造成された人工林が伐期を迎え、生態系サービスの低下を防ぎつつ、いかに森林を伐採し、木材を生産するかが大きな課題となっています。研究によると、生物多様性保全機能や保健休養機能は天然林の方が人工林よりも高い一方、他の機能は人工林と天然林の差は小さいか人工林の方が高いことが示されています。
適切な間伐や複層林化、広葉樹の導入など、多様な森林管理手法を組み合わせることで、木材生産と生態系サービスの両立を図ることが重要です。
森林環境税と生態系サービスへの支払い(PES)
日本では、森林がもつ様々な機能を維持・回復するために、地方自治体が自ら森林整備事業等を行い、その費用負担を森の恵みの受益者である県民に税金として幅広く求める「森林環境税」という制度が導入されています。これは「生態系サービスへの支払い(PES)」の一種で、高知県が2003年に全国に先駆けて導入し、その後多くの都道府県に広がりました。
このような仕組みにより、間伐等による森林の整備を計画通り進めることが可能となり、森林の生態系サービスの維持・向上に貢献しています。
市民参加の森林保全活動
地域住民やNPO、企業などが参加する森林保全活動は、森林の生態系サービスを維持すると同時に、参加者の森林に対する理解や愛着を深める効果があります。企業の森づくり活動や市民参加の植樹祭、環境教育プログラムなど、様々な形で森と人をつなぐ取り組みが各地で行われています。
おわりに:森林の恵みを未来へつなぐために

私たちは、自然がもたらす恩恵について普段は「値段」をつけて考えることはありません。しかし、その価値を定量化し、経済活動のあり方を考えることは、私たちの日常生活が気づかないところでどれだけ自然からのサービスを受けて成り立っているかについて考える良いきっかけになります。
生態系サービスは、人類にとっての直接的な資源供給サービスであると同時に、地球上の様々な物質やエネルギーを循環させる、大変重要な役割を果たしています。日頃、それが「森のおかげ」「森の恵み」と意識していないようなものまで含まれていることに気づくことが大切です。
自然とその生態系は、金銭的な価値をつけられるものですが、評価方法については今後どこまで厳密性を上げられるかが課題です。しかし、「タダではない」という認識をまず私たち一人一人がしっかり持つ必要があります。
森林の生態系サービスを持続的に享受していくためには、森林の価値を正しく認識し、適切な管理・保全を行っていくことが不可欠です。私たち一人ひとりが森林の恵みに感謝し、それを未来の世代に引き継いでいくための行動を起こしていきましょう。
参考情報
- 環境省「生物多様性と生態系サービスの経済的価値の評価」
- 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所
- 生態系と生物多様性の経済学(TEEB)
- 日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業および森林の多面的機能の評価について」
- 林野庁「森林・林業白書」