
「よし、今日はこのレシピでチャーハンを作ろう!」
レシピサイトを見ながら意気込んでいると、材料の欄に「温かいごはん…600g」という文字が。
「…えっと、600gって、お米を何合炊けばいいんだろう?」
「そもそも、お米1合って何グラムだっけ?」
料理を始めたばかりの方や、普段あまりお米を計らない方にとって、グラム表記は少し戸惑ってしまいますよね。
ご安心ください!この記事を読めば、ごはん600gに関するあらゆる疑問がスッキリ解決します。
この記事では、
- ごはん600gが何合なのかという結論
- 炊く前のお米の量との関係
- 失敗しない炊き方の科学的コツ
- カロリーや何人前に相当するのか
- 計量器具がない時の裏技
- 余ったごはんの絶品冷凍保存術
など、ごはん600gを完璧にマスターするための情報を、どこよりも分かりやすく解説します。
もうレシピのグラム表記で手が止まることはありません。さあ、一緒にお米の計量名人を目指しましょう!
【結論】ごはん600gは「炊きあがり」で約1.8合!
まず、誰もが知りたい結論からお伝えします。レシピなどで表記される「ごはん600g」は、炊きあがった状態のごはんで約1.8合に相当します。
多くの炊飯器は0.5合刻みで炊けるようになっているので、お米を1.8合、もしくは少し多めに2合炊けば、ごはん600gを十分に用意できる、と覚えておきましょう。
「炊く前のお米」なら約270g(約1.8合)
ここで一つ、絶対に間違えてはいけない重要なポイントがあります。それは、「炊く前のお米(生米)」と「炊きあがったごはん」では重さが全く違うということです。
ごはん600gを用意するために、炊く前のお米を600g計量してしまうと、とんでもない量のごはんが炊きあがってしまいます。
正しくは、炊きあがりのごはん600gを用意するには、炊く前のお米を約270g(約1.8合)計量する必要があります。
| 状態 | 重さ(グラム) | 体積(合) |
|---|---|---|
| 炊く前のお米 | 約270g | 約1.8合 |
| 炊きあがったごはん | 600g | 約1.8合 |
なぜ「合」の数字は同じなのに、グラム数だけが変わるのでしょうか?その秘密を次に解説します。
なぜ?お米が炊くと重くなるシンプルな理由
お米が炊くと重くなる理由はとてもシンプル。それは「お米が水を吸うから」です。
炊く前のお米(生米)は、炊飯の過程で水分を吸収して膨らみます。一般的に、炊きあがったごはんの重さは、元の生米の重さの約2.2倍になると言われています。
計算式で見てみましょう。
炊く前のお米(g) × 約2.2 = 炊きあがったごはん(g)
270g(約1.8合) × 2.2 ≒ 594g(約600g)
この「約2.2倍ルール」を覚えておくと、他のグラム数で指定されたときも応用が利くので非常に便利です。
一目でわかる!ごはんの「グラム・合・カロリー」早見表
ごはん600gが約1.8合ということは分かりましたが、他の量の場合はどうなるのでしょうか。日常的によく使う量について、炊飯後と炊飯前の換算表を作成しました。ぜひブックマークしてご活用ください。
炊いたごはん(炊飯後)の換算表
| 合数 | 炊きあがり重量 | カロリー目安 | お茶碗(中)の目安 |
|---|---|---|---|
| 0.5合 | 約165g | 約257kcal | 約1杯分 |
| 1合 | 約330g | 約515kcal | 約2杯分 |
| 1.5合 | 約495g | 約772kcal | 約3杯分 |
| 1.8合 | 約600g | 約936kcal | 約4杯分 |
| 2合 | 約660g | 約1,030kcal | 約4.5杯分 |
| 3合 | 約990g | 約1,544kcal | 約6.5杯分 |
※カロリーは「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」の「水稲めし 精白米 うるち米」の100gあたり156kcalとして計算。お茶碗1杯を150gとして換算。
生米(炊飯前)の換算表
| 合数 | 生米重量 | 炊きあがり目安 |
|---|---|---|
| 0.5合 | 75g | 約165g |
| 1合 | 150g | 約330g |
| 1.5合 | 225g | 約495g |
| 1.8合 | 270g | 約600g |
| 2合 | 300g | 約660g |
| 3合 | 450g | 約990g |
「お米1合」の基本を再確認しよう
ここまで「合」という単位を当たり前のように使ってきましたが、この機会に「1合」の定義をしっかりおさらいしておきましょう。重さと体積、2つの側面から理解することが重要です。
重さ(g)で測る場合:1合 = 150g
キッチンスケールなど、重さで測る場合、お米1合は150gです。これは全国どこでも共通の定義であり、お米の種類(コシヒカリ、あきたこまち等)による差もほとんどありません。グラム単位で測るのが最も正確な方法と言えます。
体積(ml/cc)で測る場合:1合 = 180ml
炊飯器に付属している計量カップなど、体積で測る場合、お米1合は180ml(180cc)です。このカップすりきり一杯がお米1合分となります。
【注意】計量カップは「お米用」と「液体用」で違う!
ここで多くの人が間違えやすいのが、「お米用の計量カップ」と「料理用の液体計量カップ」は別物だということです。
- お米用計量カップ: 1合 = 180ml
- 液体用計量カップ: 1カップ = 200ml
もし、お米用のカップが見当たらないからといって液体用のカップで「1カップ」を計ってしまうと、お米の量が20ml分多くなってしまいます。その結果、水加減もずれてしまい、炊きあがりが硬くなったり、逆にベチャッとしたりと、食感が悪くなる大きな原因になるので注意しましょう。
ごはん600gを炊飯器で炊く!失敗しない黄金ステップ

ごはん600g(お米1.8合)を炊くための、具体的な手順を4つのステップでご紹介します。それぞれの工程に美味しく炊き上げるための科学的な理由があります。基本を押さえて、ふっくら美味しいごはんを炊きあげましょう。
ステップ1:お米を正確に計量する(270g)
まずは、炊く前のお米を270g用意します。
最も正確なのはキッチンスケールを使う方法です。ない場合は、お米用の計量カップ(180ml)でまず1合(150g)を計り、その後、カップの8分目(0.8合=約120g)まで入れて合計270gとします。
ステップ2:優しく研いで、しっかり水を切る
お米をボウルに入れ、たっぷりの浄水またはミネラルウォーターを注ぎ、さっとかき混ぜてすぐに水を捨てます。これは、お米が乾燥しているため、最初に触れた水を最も吸収しやすく、米ぬかの匂いが移るのを防ぐためです。その後、水を切った状態で、指を立ててシャカシャカと優しくかき混ぜるように20回ほど研ぎます。これを2〜3回繰り返します。
ポイント:ゴシゴシと力を入れて研ぐと、お米が割れてデンプンが流れ出し、ベチャついた炊きあがりの原因になるので禁物です。優しく、しかしスピーディーに行いましょう。
ステップ3:炊飯器の「1.8合」の目盛りに合わせて水を入れる
研いだお米を炊飯釜に入れ、平らにならします。炊飯器の内釜には「白米」や「すしめし」などの目盛りが刻まれています。「白米」の「1.8」の線まで水を注ぎます。もし1.8の目盛りがない場合は、1.5と2の中間より少し上を目安に水を入れましょう。
ポイント:ここですぐに炊飯スイッチを押さず、夏場は30分、冬場は1時間ほど浸水させましょう。お米の芯まで水分を行き渡らせることで、デンプンが十分に糊化(アルファ化)し、ふっくらと甘みのあるごはんに炊きあがります。
ステップ4:炊きあがったら「ほぐし」を忘れずに
炊飯が終わったら、すぐに蓋を開けずに10〜15分ほど蒸らします。これにより、釜の中の水分が均一になり、ごはんの美味しさが安定します。
蒸らし終わったら、しゃもじで釜の底からごはんを十字に切り、底から持ち上げるようにして優しくほぐします。これは「天地返し」とも呼ばれ、余分な水分を飛ばし、炊きムラをなくすための非常に大切な工程です。ほぐすことで、一粒一粒が際立った美味しいごはんになります。
計量カップ・スケールがない!そんな時の代用テクニック

「いざ炊こうと思ったら、キッチンスケールも計量カップも見当たらない!」そんな緊急事態でも大丈夫。身近なもので代用するテクニックを3つご紹介します。精度は多少落ちますが、覚えておくと非常に役立ちます。
大さじスプーンで計る方法
多くの家庭にある大さじスプーン(15ml)は、すりきり1杯で約12gのお米が計れます。
お米270g(1.8合) ÷ 12g ≒ 大さじ22.5杯
少し手間はかかりますが、これが一番手軽で正確性の高い方法かもしれません。
ペットボトルのキャップで計る方法
一般的な飲料のペットボトルキャップは、容量が約7.5mlです。お米に換算すると約6gになります。
お米1合(150g) ÷ 6g = キャップ25杯
お米1.8合(270g)を炊くには、キャップ約45杯(25杯 × 1.8)が必要になります。
牛乳パックで計る方法
1リットル(1000ml)の牛乳パックの底は、一般的に一辺が約7cmの正方形です。この牛乳パックの底から約3.6cmの高さまでお米を入れると、約1合(180ml)になります。
(計算式:7cm × 7cm × 3.6cm ≒ 176.4ml)
定規があれば、簡易的な計量カップとして使用できます。
ごはん600gって、どのくらいの量?何人前?
ごはん600gが具体的にどれくらいのボリュームなのか、身近なものでイメージしてみましょう。これを知っておくと、レシピの分量を調整する際に役立ちます。
お茶碗(中サイズ)で約4杯分
一般的に、お茶碗に軽く一杯盛ったごはんの量は約150gです。
600g ÷ 150g = 4杯
つまり、ごはん600gは、お茶碗でちょうど4杯分に相当します。
コンビニのおにぎりで約6個分
コンビニで売られている標準的なおにぎりのごはん量は、具材を除いて約100gです。
600g ÷ 100g = 6個
おにぎりにすると、約6個分作れる計算になります。
何人前に相当する?シーン別目安
ごはん600gが何人前になるかは、食べる人の年齢や性別、そしてメニューによって大きく変わります。以下の表を目安にしてください。
| シーン | 目安人数 | 一人当たりの量のイメージ |
|---|---|---|
| 成人男性がメインの夕食 | 2〜3人前 | 200g(大盛り)〜300g(特盛り) |
| 成人女性がメインの夕食 | 3〜4人前 | 150g(普通盛り)〜200g(大盛り) |
| 家族4人(大人2人、子供2人)の丼もの | ちょうど良い | 親:各200g、子:各100g |
| 手巻き寿司やちらし寿司 | 2〜3人前 | 具材もたくさん食べるため、一人前を多めに見積もる |
| 育ち盛りの子供がいるチャーハン | 2人前 | 一人300gの大盛りチャーハン |
このように、家族構成や作る料理に合わせて2〜4人前と考えると良いでしょう。
知っておきたい!ごはん600gのカロリーと糖質量

健康やダイエットに関心のある方にとって、カロリーや糖質量は気になるところですよね。正確な知識を身につけ、上手にコントロールしましょう。
カロリーは約936kcal
文部科学省の「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」によると、精白米(うるち米)のごはんは100gあたり156kcalです。
156kcal × 6 = 936kcal
ごはん600gの総カロリーは約936kcalとなります。これは、食パン(6枚切り)に換算すると約6枚分に相当し、成人女性の1日の摂取カロリー目安(約2000kcal)の半分近くを占めます。
糖質量は約220g
同じく食品標準成分表に基づき、糖質量を計算します。ごはん100gあたりの炭水化物量は37.1g、そのうち食物繊維は0.5gです。糖質量は炭水化物から食物繊維を引いて計算します。
糖質量(100gあたり) = 37.1g – 0.5g = 36.6g
36.6g × 6 = 219.6g
ごはん600gの総糖質量は約220gとなります。これはうどん(ゆで)に換算すると約4玉分に相当します。
カロリー・糖質を抑える食べ方の工夫
ごはんが好きだけど、カロリーや糖質が気になる…という方は、以下のような工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。
- 玄米や雑穀米、もち麦を混ぜる: 白米に比べて食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を抑える効果(低GI)が期待できます。
- 野菜やきのこ、海藻類と一緒に食べる: 食事の最初に食物繊維が豊富な副菜を食べる「ベジファースト」は、糖の吸収を穏やかにしてくれます。
- よく噛んでゆっくり食べる: 咀嚼回数を増やすことで満腹中枢が刺激され、少量でも満足感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぎます。
- 冷やご飯にする: ごはんが冷めることで、一部のデンプンが消化されにくい「レジスタントスターチ」に変化します。これは食物繊維と似た働きをし、血糖値の上昇を抑えたり、腸内環境を整えたりする効果が期待できます。おにぎりや、一度冷ましたごはんを温め直して食べるのがおすすめです。
ごはん600gで作る!おすすめ絶品レシピ3選
ごはんが600gあると、家族が喜ぶ美味しいメニューが作れます。ここでは、初心者でも失敗しない定番からアレンジまで3つのレシピを、ポイント付きで詳しくご紹介します。
レシピ1:家族で楽しむ!黄金パラパラチャーハン
お店のようなパラパラのチャーハンを作るコツは、ごはんを炒める前に卵と混ぜておくこと。ごはん一粒一粒が卵でコーティングされ、ベチャッとなるのを防ぎます。
材料(3〜4人分): 温かいごはん600g、卵3個、長ネギ1/2本、焼き豚100g、鶏がらスープの素 小さじ2、醤油 小さじ2、塩コショウ 少々、サラダ油 大さじ2
作り方:
- 長ネギと焼き豚は粗みじん切りにする。ボウルに卵を溶きほぐし、温かいごはんを入れて、しゃもじで切るように混ぜ合わせる(卵かけごはんの状態にする)。
- フライパンにサラダ油を熱し、強火で長ネギと焼き豚を香りが出るまで炒める。
- 1のごはんを加えて、フライパン全体に広げ、木べらやヘラでごはんをほぐしながら、切るように炒める。
- ごはんがパラパラになったら、鶏がらスープの素、塩コショウで味付けし、最後に鍋肌から醤油を回し入れて香りをつけ、さっと混ぜたら完成。
レシピ2:パーティーの主役!本格手巻き寿司
特別な日には、みんなでワイワイ楽しめる手巻き寿司がおすすめです。酢飯にすることで、さっぱりとたくさん食べられます。
材料(3〜4人分): 炊きたてのごはん600g、寿司酢(酢 大さじ4、砂糖 大さじ2.5、塩 小さじ1.5)、お好みの具材(マグロ、サーモン、きゅうり、卵焼き、アボカド、ツナマヨなど)、焼きのり
作り方:
- 寿司酢の材料をよく混ぜ合わせておく。
- 大きめのボウルや飯台に炊きたてのごはんを入れ、寿司酢をしゃもじに伝わせながら全体に回しかける。
- うちわで扇いで粗熱を取りながら、しゃもじでごはんを切るように混ぜる。粘りが出ないように手早く行うのがポイント。
- 人肌程度に冷めたら、固く絞った濡れ布巾をかけて乾燥を防ぐ。お好みの具材を準備し、焼きのりで巻いていただく。
レシピ3:作り置きに便利!鶏五目ごはん
具沢山の炊き込みごはんは、栄養バランスも良く、作り置きやお弁当にもぴったりです。冷めても美味しいのが魅力です。
材料(お米1.8合分): お米270g(1.8合)、鶏もも肉100g、にんじん1/4本、ごぼう1/4本、しいたけ2枚、油揚げ1/2枚、[A]だし汁、[A]醤油 大さじ2、[A]みりん 大さじ2、[A]酒 大さじ1
作り方:
- お米は研いで30分以上浸水させ、ザルにあげて水気を切っておく。
- 鶏もも肉、油抜きした油揚げ、野菜はすべて5mm角程度に細かく切る。ごぼうはささがきにして水にさらす。
- 炊飯器にお米を入れ、[A]の調味料をすべて加える。その後、1.8合の目盛りまでだし汁(または水)を注ぎ、軽く混ぜる。
- 2の具材をお米の上に乗せ、平らにならして通常通り炊飯する。(具材は混ぜずに乗せるのがポイント)
- 炊きあがったら10分蒸らし、全体をさっくりと混ぜて完成。
余ったごはん、どうしてる?専門家が教える冷凍保存の極意
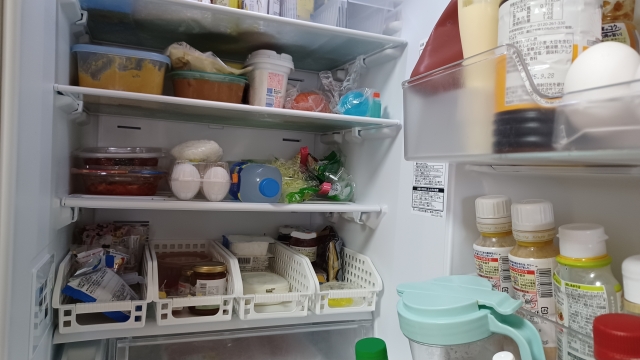
ごはんを多めに炊いて、余ってしまうこともありますよね。そんな時、あなたは冷蔵庫に入れますか?それとも冷凍庫?実は、美味しさを保つなら「冷凍保存」が断然おすすめです。
冷蔵保存より「冷凍保存」が圧倒的におすすめな理由
ごはんの主成分であるデンプンは、0〜4℃の温度帯(冷蔵庫の温度)で最も「老化(β化)」が進み、水分が抜けてパサパサでまずくなってしまいます。これはパンが冷蔵庫で硬くなるのと同じ現象です。
一方、-18℃以下の冷凍庫で急速に凍らせることで、デンプンの老化を防ぎ、炊きたての美味しさをキープすることができるのです。
美味しさを保つ!冷凍・解凍の鉄則
お米の専門家である「五ツ星お米マイスター」も推奨する、冷凍・解凍のコツをご紹介します。このひと手間で、冷凍ごはんの味が劇的に変わります。
- 炊きたての「湯気が上がっている状態」でラップに包む: ごはんが持つ水分(湯気)ごと閉じ込めることで、解凍した時に水分がごはんに戻り、ふっくらと仕上がります。
- 1食分ずつ(約150g〜200g)平たく包む: 熱いですが、頑張って薄く平らにすることで、急速に冷凍でき、解凍時も加熱ムラがなくなります。
- 粗熱が取れたら、金属トレーに乗せて冷凍庫へ: 熱伝導の良い金属トレーに乗せることで、より早く冷凍することができます。
- 解凍は「電子レンジ」で一気に加熱する: 自然解凍は水分が抜けてしまう原因に。ラップに包んだまま、電子レンジで一気に温めるのが正解です。600Wで2分〜3分が目安です。
この方法で保存すれば、1ヶ月程度は美味しく食べることができます。チャーハンや雑炊、ドリアなどに活用するのもおすすめです。
【応用編】玄米や雑穀米で600g炊きたい場合は?
健康志向の高まりから、玄米や雑穀米を食べている方も多いでしょう。白米以外のお米で600g炊きたい場合のポイントを解説します。
基本の考え方は白米と同じ
玄米や雑穀米の場合でも、炊きあがりの重さが生米の約2.2倍になるという基本は大きく変わりません。そのため、炊きあがり600gを目指すなら、炊く前のお米は約270g(1.8合)という計算で問題ありません。
水加減と浸水時間は製品の表示を要確認!
ただし、白米と大きく異なるのが「水加減」と「浸水時間」です。
玄米は表面が硬い糠(ぬか)層で覆われているため、白米よりも水を吸いにくく、1.5倍程度の水と6時間以上の長い浸水時間が必要です。雑穀米も、ブレンドされている雑穀の種類によって最適な水分量が変わってきます。
多くの炊飯器には「玄米モード」が搭載されており、専用の目盛りが付いています。雑穀米の場合は、製品パッケージに記載されている水加減の指示に従うのが最も確実です。
よくある質問(Q&A)

ごはんの計量や炊飯に関する、よくある質問にお答えします。
Q1. 古米と新米で水の量は変えるべき?
A1. はい、変えるのがおすすめです。
新米(その年に収穫されたお米)は水分を多く含んでいるため、水の量をいつもより少し(大さじ1杯程度)減らすと、ベチャッとせず美味しく炊けます。逆に、古米は水分が少ないため、少し多めに水を入れるとふっくら仕上がります。
Q2. 無洗米の場合はどうすればいい?
A2. お米の量を少し多めにし、水も少し多めにします。
無洗米は、普通のお米についている肌ぬかが取り除かれているため、同じ1カップでも米粒の量が多くなります(約5%増)。そのため、計量カップで計る場合は、専用のカップを使うか、普通米よりも大さじ1〜2杯多く水を入れると良いとされています。詳しくは炊飯器の指示や無洗米のパッケージをご確認ください。
Q3. 炊飯器ではなく鍋で炊く場合の水の量は?
A3. お米の体積の1.2倍が目安です。
鍋で炊く場合、水分の蒸発量が多いため、炊飯器よりも多めの水が必要です。お米1.8合(約324ml)の場合、水は約390mlが目安となります。(計算式:324ml × 1.2 ≒ 389ml)
鍋の種類や火加減によっても変わるので、何度か試してお好みの固さを見つけるのがおすすめです。
Q4. 炊飯器の「早炊きモード」を使ってもいいですか?
A4. 時間がない時は便利ですが、味は通常モードに劣る場合があります。
早炊きモードは、浸水や蒸らしの時間を短縮して炊き上げる機能です。そのため、お米の芯が少し残ったり、甘みが引き出されにくかったりすることがあります。時間がある時は、じっくり時間をかける通常炊飯がおすすめです。
Q5. 保温したごはんは、いつまで美味しく食べられますか?
A5. 美味しく食べられるのは5〜6時間が限界と言われています。
長時間の保温は、ごはんの水分が飛んで黄ばみや匂いの原因になります。6時間を超える場合は、本記事で紹介した方法で冷凍保存に切り替えるのが賢明です。
まとめ:ごはん600gをマスターして、もっと料理を楽しもう!

今回は、「ごはん600gは何合?」という素朴な疑問から、正しい計量方法、美味しい炊き方、カロリー、保存方法まで、幅広く掘り下げてきました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- ごはん600gは、炊きあがった状態で約1.8合。
- 炊く前のお米(生米)で用意する場合は約270g。
- お米は炊くと水分を吸って約2.2倍の重さになる。
- お米1合は、重さなら150g、体積なら180ml。
- 余ったごはんは、炊きたてをラップに包んで「冷凍保存」が鉄則!
レシピのグラム表記は、一見すると難しく感じるかもしれません。しかし、一度基本を理解してしまえば、もう何も怖いことはありません。
この記事が、あなたの料理ライフをより豊かで楽しいものにする一助となれば幸いです。今日から自信を持って、ごはんを計量し、美味しい料理作りに挑戦してみてくださいね!

